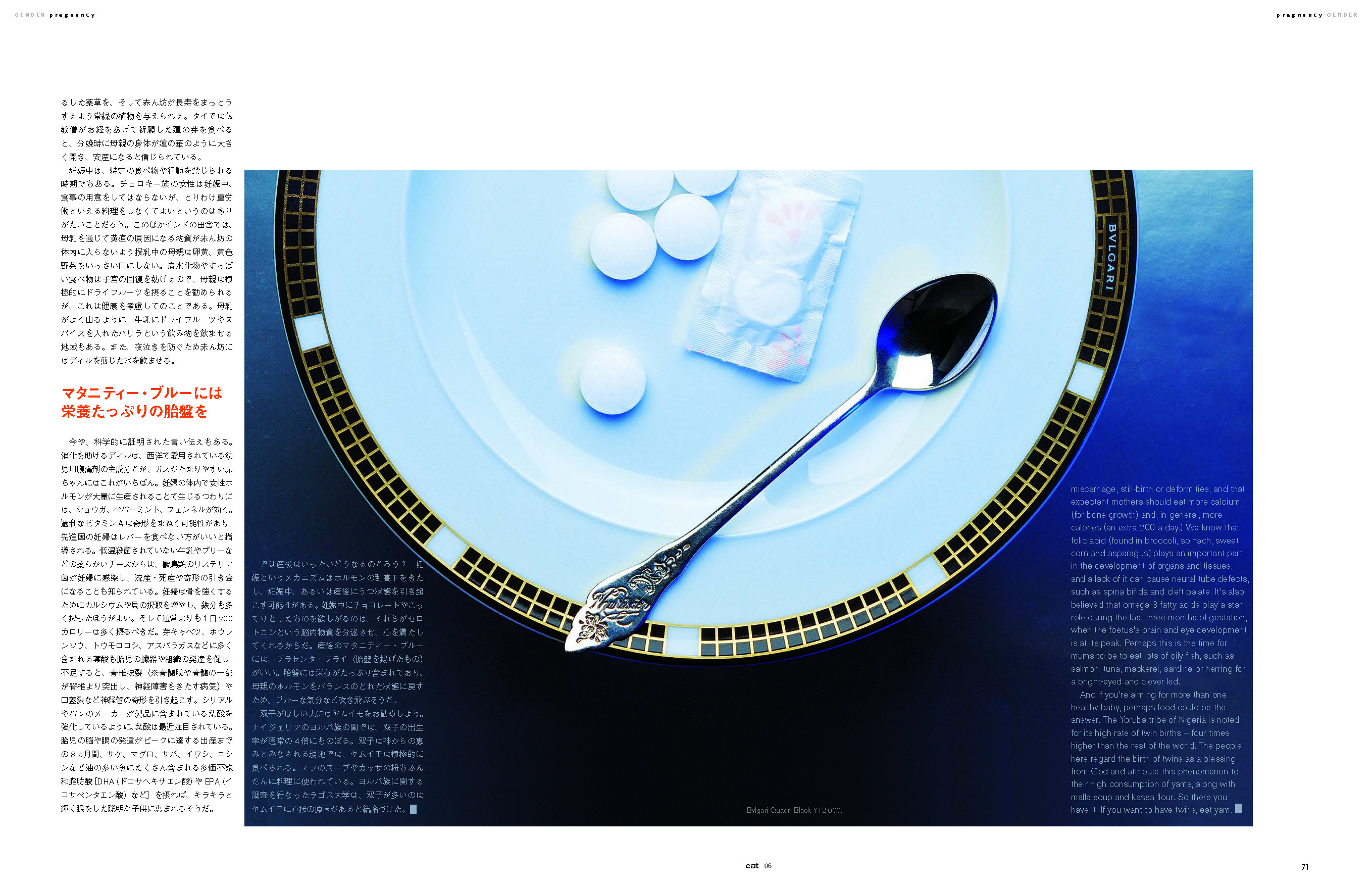妊婦と食のミステリー
Eat 6号: ジェンダー

この記事は2001年8月に公開されたものです。
妊婦が匂いに敏感になることはよく知られた事実である。だが、妊娠期間中に現れる独特な食の嗜癖については、実はよくわかっていないことも多い。科学的根拠のあるものから迷信、言い伝えまで、妊婦と食にまつわる謎を追ってみた。
「妻がいきなり、朝5時に起きてピーナッツバターサンドを作りだしたんだ。普段は絶対食べないのに」
「とにかく彼女の食欲はどうしようもなくて、夜中に車を飛ばしてサモサを売っている24時間営業のテイクアウトを探したよ。それからはいつも冷凍庫にストックしたけど、まあこんなのは序の口だね」
「妻が防虫剤なしではいられなくなってしまって。さすがに食べはしなかったけど、いつもエプロンやポケットに忍ばせて、あのナフタリンの匂いを一日中嗅いでいるんだ。おかげで家は防虫剤だらけさ」

以上はめでたく父親になった3人の証言だが、妊娠した妻を見守ってきた世の男性なら皆、共感できるのではないだろうか?妊婦がある食べ物を大量に欲しがるのは日常茶飯事だが、実はその理由はよくわかっていない。食べ物だけでなく、一風変わったものを欲しがる妊婦もいる。あるエクアドル女性によると、彼女の母親はとにかく生のコーヒー粉と砂糖を混ぜたものを食べずにいられなかったらしい。想像するだけで気持ち悪くなるものを欲しがる妊婦もいる。ドクター・フルニエというフランス人が1812年に出版した医学辞典には、就寝中の夫の肌に傷をつけ、そこから血を吸っていたという妊婦の症例が載っている。
これはかなり珍しいとしても、食べられないものを欲しがるケースはある。食用に適さないものを食べたがる倒錯した食欲のことを異食症という。語源はカササギを意味するラテン語で、この鳥がなんでも食べることに由来しているが、チョーク、炭、土などを欲しがる異食症は珍しくない。鉄分など不足している栄養素を補おうとして起きる症状じゃないかという説もあったが、今は疑問視されている。逆に、好物だったものが突然嫌いになるということもある。カレーが大好物だったロザリーはこう話す。
「息子がおなかにいる時、一夜で嫌いになったの。匂いも耐えられなかった。息子が生まれてからも、いまだに食べられない」これは珍しい例で、いったん好物を嫌いになっても、出産後はたいていまた、好きになるものだ。
なぜこのような現象が起きるのか。科学的にはほとんど証明されていない。ただ、歴史背景や文化の違いにかかわらず、妊婦と食べ物には深いつながりがあり、妊娠中に特定の食べ物を口にすると、生まれてくる子供の性別や気質を左右できるという考え方は世界各地で耳にする。

特に男の子が望まれる文化では、生まれてくる赤ん坊の性別を決めることはとても大切で、何を食べ、何を避けるかについてもさまざまな迷信や言い伝えがある。食べ物以外でも、男の子を産む方法があるという。個人的に気に入っているのは性交時、女性が先にオーガズムに達すれば男の子が生まれるというユダヤ教の言い伝えだ。これは無私無欲なユダヤ男性に対するタルムード教典の報いなのだろうか?
オーガズムはさておき、食べ物の役割は重要だ。19世紀のドイツの研究は、砂糖を減らした食事によって男の子が生まれる、と論じている。同様にフランスの研究では、肉、ジャガイモ、豆、アーティチョーク、あんずなどカリウムや塩の多い食事は男の子を、乳製品、卵、グレープフルーツ、ラディッシュ、かぶ、緑黄色野菜など、カルシウムやマグネシウムのふんだんな食事は女の子をもたらすと述べている。ボブ・ゲルドフとの間に3人の娘をもうけたポーラ・イエーツは、男の子が欲しければ腿の内側をレタスでこするとよいとアドバイスされたが、結局4番目の子供も女の子だったそうだ。
妊婦と食べ物にまつわるタブーや言い伝え
胎内でモーツアルトを聞いていた赤ん坊は、誕生後もモーツアルトが好きになるというように、子供は音楽の好みを父親か母親から譲り受けると言われるが、食べ物の好みもそれと同様だ。すっぱいものが好きならピクルスやチリが大好き、あるいは大嫌いになる可能性が大きく、好きでも嫌いでもないという中間はないらしい。科学的根拠がないにもかかわらず、妊婦と食べ物にまつわるタブーや言い伝えはいろいろある。オーストラリアのアボリジニは、生まれてくる子供の魂が夫から妻に与えられる食べ物の中にあると信じている。第三世界の信仰では、夫の役割が重視されているようだ。アフリカに住むガー族の場合、夫が妻を「一族の樹」の元へと連れてゆき、妻はそこでもらった聖水で清められた樹の葉をスポンジのように使って身体を拭う。ニャニャとよばれるこの葉は乾燥され、後日、分娩が長引きそうな場合、お茶にして飲むのだそうだ。また、ガー族の女性は分娩時に赤ん坊がつるりと滑り出してくるようにぬるぬるした薬草を、そして赤ん坊が長寿をまっとうするよう常緑の植物を与えられる。タイでは仏教僧がお経をあげて祈願した蓮の芽を食べると、分娩時に母親の身体が蓮の華のように大きく開き、安産になると信じられている。
妊娠中は、特定の食べ物や行動を禁じられる時期でもある。チェロキー族の女性は妊娠中、食事の用意をしてはならないが、とりわけ重労働といえる料理をしなくてよいというのはありがたいことだろう。このほかインドの田舎では、母乳を通じて黄疸の原因になる物質が赤ん坊の体内に入らないよう授乳中の母親は卵黄、黄色野菜をいっさい口にしない。炭水化物やすっぱい食べ物は子宮の回復を妨げるので、母親は積極的にドライフルーツを摂ることを勧められるが、これは健康を考慮してのことである。母乳がよく出るように、牛乳にドライフルーツやスパイスを入れたハリラという飲み物を飲ませる地域もある。また、夜泣きを防ぐため赤ん坊にはディルを煎じた水を飲ませる。

マタニティー・ブルーには栄養たっぷりの胎盤を
今や、科学的に証明された言い伝えもある。消化を助けるディルは、西洋で愛用されている幼児用腹痛剤の主成分だが、ガスがたまりやすい赤ちゃんにはこれがいちばん。妊婦の体内で女性ホルモンが大量に生産されることで生じるつわりには、ショウガ、ペパーミント、フェンネルが効く。過剰なビタミンAは奇形をまねく可能性があり、先進国の妊婦はレバーを食べない方がいいと指導される。低温殺菌されていない牛乳やブリーなどの柔らかいチーズからは、獣鳥類のリステリア菌が妊婦に感染し、流産・死産や奇形の引き金になることも知られている。妊婦は骨を強くするためにカルシウムや貝の摂取を増やし、鉄分も多く摂ったほうがよい。そして通常よりも1日200カロリーは多く摂るべきだ。芽キャベツ、ホウレンソウ、トウモロコシ、アスパラガスなどに多く含まれる葉酸も胎児の臓器や組織の発達を促し、不足すると、脊椎披裂(※脊髄膜や脊髄の一部が脊椎より突出し、神経障害をきたす病気)や口蓋裂など神経管の奇形を引き起こす。シリアルやパンのメーカーが製品に含まれている葉酸を強化しているように、葉酸は最近注目されている。胎児の脳や眼の発達がピークに達する出産までの3カ月間、サケ、マグロ、サバ、イワシ、ニシンなど油の多い魚にたくさん含まれる多価不飽和脂肪酸[DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(イコサペンタエン酸)など]を摂れば、キラキラと輝く眼をした聡明な子供に恵まれるそうだ。では産後はいったいどうなるのだろう?妊娠というメカニズムはホルモンの乱高下をきたし、妊娠中、あるいは産後にうつ状態を引き起こす可能性がある。妊娠中にチョコレートやこってりとしたものを欲しがるのは、それらがセロトニンという脳内物質を分泌させ、心を満たしてくれるからだ。産後のマタニティー・ブルーには、プラセンタ・フライ(胎盤を揚げたもの)がいい。胎盤には栄養がたっぷり含まれており、母親のホルモンをバランスのとれた状態に戻すため、ブルーな気分など吹き飛ぶそうだ。双子がほしい人にはヤムイモをお勧めしよう。ナイジェリアのヨルバ族の間では、双子の出生率が通常の4倍にものぼる。双子は神からの恵みとみなされる現地では、ヤムイモは積極的に食べられる。マラのスープやカッサの粉もふんだんに料理に使われている。ヨルバ族に関する調査を行なったラゴス大学は、双子が多いのはヤムイモに直接の原因があると結論づけた。
文/ クリスティン・ブース 写真/ 小野里美